ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- ホーム
- IIJについて
- 情報発信
- 広報誌(IIJ.news)
- IIJ.news Vol.190 October 2025
- 未来をつくるデータセンター ~環境対策と省エネ効率を追求するエンジニアの挑戦
サステナ・レポート 未来をつくるデータセンター ~環境対策と省エネ効率を追求するエンジニアの挑戦
IIJ.news Vol.190 October 2025
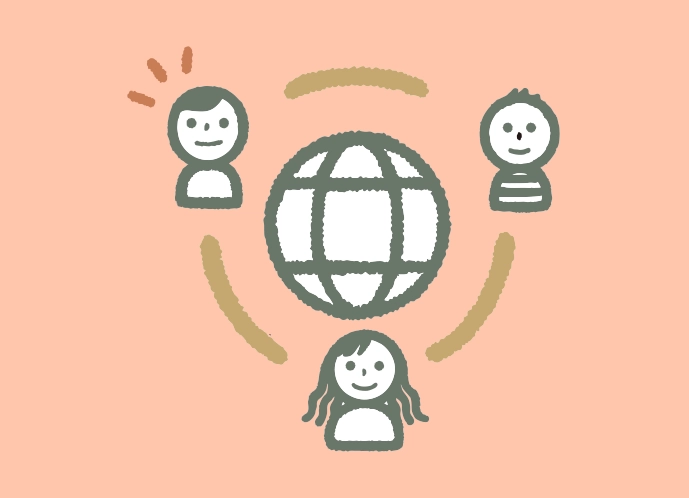
サステナブルな未来に向けた活動にチャレンジしているIIJの社員を紹介する「サステナ・レポート」。第3回は、データセンター(DC)の構築に携わっている堤優介さんです。

紹介する社員
IIJデータセンターサービス部 データセンター基盤技術課長
堤 優介
執筆者プロフィール
IIJ 執行役員 経営戦略本部 サステナビリティ委員会 事務局長
川上 かをり
——堤さんのキャリアを教えてください。
堤:
2015年にIIJに中途入社し、一貫してDCの設計や構築、DCで利用する技術の開発をしています。
——今、注力している分野は?
堤:
DCの環境対策と、AI利用などで高密度化するサーバ向けの水冷技術の研究開発です。米NVIDIAなど海外勢が先行するAIインフラに関して、国内でも強化していくことを国が進めていて、株式会社Preferred Networksと北陸先端科学技術大学院大学と共同で国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の公募に採択されました。IIJはDCインフラを担当しています*1。
——どんなところに仕事のやりがいを感じますか?
堤:
社会規模の課題解決につながる取り組みに携わっているところです。環境対策や脱炭素化が国際的な潮流となり、国内もデジタル化・グリーン化に向かっています。DCはその両方に関わっていますが、まだ過渡期でこれから市場が広がっていく領域が多く、今は手探りでやっていることや些細な発見が、将来に大きな影響を与えたり、デファクトスタンダードになる可能性がある。そのあたりにやりがいを感じています。
—— IIJならではの技術はありますか?
堤:
DCの空調に外気を使っています。一般には大量の電気を使う熱交換用設備でサーバの熱を除いていますが、IIJのDCでは外気を活用することで高い省エネ性能を実現しています。PUE*2では、資源エネルギー庁のベンチマーク制度で1.4以下という目標が設定されていますが、IIJのDCはすでに業界最高水準の1.3台を達成しています。松江DCに外気冷却を導入したのは15年ほど前ですが、現在も高い省エネ性にこだわっています。一般にDCの空調はサーバ室の温湿度を見て制御しますが、IIJではサービス運用部門と連携してサーバの稼働状況を把握できるようにし、「この曜日にバッチ処理が当たって、この時間帯に電力利用が増える」といった利用傾向も見ながら、空調制御に活かしています。
——サービス提供者だからこそできるDC運用ですね。
堤:
白井DCの一期棟でのこの取り組みは、施工会社の高砂熱学工業と協力して作り、空調・衛生工学会賞技術賞をいただきました*3。省エネは環境対策だけでなく、電気コストを下げるメリットもあり事業面でも重要です。
——「水冷技術」の開発は、どのような状況ですか?
堤:
今はまだメーカ各社の仕様もさまざまで、水冷に対応するDCであることが強みになる段階ですが、IIJではその先の省エネ性や効率性までを見据えた研究開発を進めています。これまでも国内では標準でなかった外気冷却方式を採用してイニシアティブをとってきたので、水冷技術でも業界をリードして環境性能の高い次世代DC基盤の実用化を進めていきたいです。
- *1https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2023/1205.html
- *2PUE (Power Usage Effectiveness):DCの電力使用効率を示す指標で1.0に近づくほど効率的とされる。
- *3https://www.iij.ad.jp/news/iijnews/vol_182/index.html

白井DC外観。カーボンニュートラルデータセンターとして、IT機器の排熱対応にさまざまな空調技術や冷却技術を採用し、電力利用効率の向上に取り組んでいる。
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです