ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- ホーム
- IIJについて
- 情報発信
- 広報誌(IIJ.news)
- IIJ.news Vol.190 October 2025
- 再録「インターネット・トリビア」モバイル編
MVNOの進化とIIJmioの挑戦――IIJが描くモバイル戦略 再録「インターネット・トリビア」モバイル編
IIJ.news Vol.190 October 2025
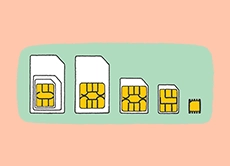
小誌で長年連載している「インターネット・トリビア」のなかから、過去に取り上げた“モバイル”に関する記事をピックアップ!
執筆者による解題「2025年の視点」を新たに加え、“モバイル”の軌跡を振り返る。
IIJ広報部 技術統括部長
堂前 清隆
Trivia1 SIMカード
IIJ.news vol.119(2013年12月号)掲載
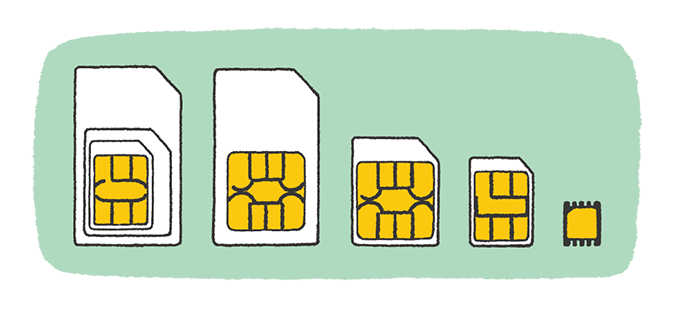
個人向けを中心に、安価なモバイル通信サービスが脚光を浴びています。従来、モバイル通信サービスは、スマートフォンやモバイルルータなどの通信機器とセットで提供されることが一般的でしたが、最近の安価なサービスは機器とセットではなく、「通信サービス」だけを提供しています。そしてここで活躍するのが「SIMカード」です。
SIMカードは、指先程度のサイズの小さなカードです。スマートフォンやモバイルルータだけでなく、通話がメインの「フィーチャーフォン」にも取り付けられています。
このカードには、1枚1枚異なる固有のIDが書き込まれており、これが通信サービスの利用者を識別するために使われます。冒頭で紹介したようなサービスでは、契約を結ぶと、SIMカードだけが手元に届けられ、利用者が自分で調達した端末にカードを取り付け、通信サービスを利用するという手順になっています。
日本でSIMカードが本格的に導入されたのは、第3世代(3G)の通信サービスからです。それ以前は、携帯電話機本体に契約者を識別するためのIDが書き込まれており、新しい携帯電話端末に交換する時は、携帯ショップで端末に書き込まれているIDを契約管理システムに登録し直す必要がありました。それがSIMカードの導入により、カードを新しい端末に差し替えるだけでよくなりました。携帯ショップで「機種変」を行なう時も、店員はカードを新しい端末に差し替えて渡してくれます。
ところでこのSIMカード、単にIDが書き込まれているだけでなく、とても小さなコンピュータが内蔵されており、これを利用すれば、暗号化などの高度な処理を行なうことができます。例えば、スマートフォンのNFC(近距離無線通信)を利用した「おさいふケータイ」サービスは、認証に関する処理をSIMカード内のアプリケーションと協調して動作することで実現しています。
小さなカードですが、案外重要な役目を持っているのです。
2025年の視点
記事を書いた2013年は「格安スマホ(格安SIM)」がブレイクする直前でした。当時は、携帯電話ショップのスタッフがSIMカードを取り付けて電話機ごとお渡しするのが一般的で、SIMカードの存在に気づいていない方も大勢いらっしゃいました。そして2020年頃から、SIMカードに相当する部品をスマホ内に組み込んで、データをダウンロードして書き換えるタイプの「eSIM」が普及しました。一時期、皆さんが手に取っていたSIMカードは、再びその存在を意識しないものになっていくのかもしれません。
Trivia2 携帯電話の電話番号が足りない!
IIJ.news vol.156(2020年2月号)掲載

国内の携帯電話(スマートフォンやPHSなどを含む)は、2001年の時点では6千万~7千万契約程度でしたが、2011年には1億2千万契約を超え、計算上「1人1台」を突破しました。その後も契約は伸び続け、2019年には1億8千万契約に達しています。そして、携帯電話の契約はまだまだ伸びると予測されています。
これだけ多くの携帯電話が使われると、さまざまなものが足りなくなってきます。その1つが電話番号です。電話は国際電話を経由して他の国ともつながっているため、国内の電話番号も、国際機関(ITU-T)が定めたルールにもとづいて使わなければなりません。そのため、日本で利用可能な電話番号の数には限りがあります。有限な資源である電話番号を、携帯電話、固定電話、IP電話などでどのように使い分けるかという「電話番号計画」は、日本では総務省が担当しています。
総務省の資料によると、一般的な携帯電話やスマートフォンで使われている090・080・070から始まる11桁の番号は、合計で2億7千万の番号が用意されています。ずいぶん多いように感じますが、これらの番号のうち90.4パーセントはすでに分割して各携帯電話会社に割り当てられており、残りはごくわずかです。このため、今後、携帯電話に利用するために、060で始まる番号から最大9千万追加することが予定されています。
一方、電話番号の割り当てを受けた携帯電話会社でも、電話番号をできるだけ節約して利用することが求められています。その1つの取り組みが、電話番号の再利用です。新しく契約した携帯電話に新しい電話番号を割り当てるのではなく、解約によって未使用になった電話番号をもう一度割り当てるのです。解約から再利用のあいだにはある程度の期間が空けられますが、久しぶりに電話をかけると全く違う人に電話がつながった、といったことも起こってしまいます。最近では、フリマアプリなどで電話番号を使って会員登録することもありますが、携帯電話の解約前にアプリの会員登録を抹消しておかないと、まったく無関係な人が以前の利用者としてアプリを使えてしまうといった事故も起こり得ます。
スマートフォンや携帯電話のように人が持ち歩く機器だけでなく、人が直接利用しない「IoT機器」のなかにも携帯電話網への接続機能を持ったものがあり、こうした機器も電話番号を消費します。そしてIoT機器は、人間が使う機器と比べて、1人が使う台数が圧倒的に多くなる可能性があります。例えば、農業の省力化を行なうためのあるプロジェクトでは、約7ヘクタールの水田に400個のIoT機器を設置し、インターネット経由で数人の農家の方が管理しています。もしこれらの機器の1つひとつが携帯電話網への通信機能を持った場合、数人で400個もの通信機、つまり400の電話番号を利用することになります。これは、人が持つものと比べると桁違いに大量の電話番号を消費することになります。
このようにIoT機器が携帯電話網を活用する時代の到来に備えて、総務省は通話や人間のコミュニケーション以外の用途で利用するために、020から始まる8千万の電話番号を用意しました。現在、携帯電話各社やMVNOで音声通話をともなわない「IoT用」の通信契約を行なうと、020番号が割り当てられます。しかし、この8千万は一時しのぎにしかならず、2022年には使い尽くすだろうと考えられています。さらなる対策として、総務省は020番号の桁数を11桁から14桁に拡張することを予定しています。これにより、最大100億の電話番号を追加できるようになるそうです。
なお、電話番号が拡張されるのはあくまでIoT用の契約のみです。人間が利用する一般的な携帯電話・スマートフォンは、従来どおり11桁のままですので、御安心ください。
2025年の視点
携帯電話番号の不足は、この記事を書いたあとも続いています。記事中では「2019年に1億8千万回線に達した」とありますが、なにしろ2024年末には2億2千万回線を超えており、その成長(と、それにともなう不足)はとどまるところを知りません。電話番号の再利用も続いていますが、「新しく契約した電話なのに、前の利用者宛と思われる間違い電話がかかってきた!」といった話もちらほら聞かれ、少々気がかりです。なお、これまで慣れ親しんできた「090/080/070」に加え、2026年からは「060」で始まる番号の利用も開始される予定です。
Trivia3 スマートフォンの電波を確保する周波数再編と共用
IIJ.news vol.168(2022年2月号)掲載
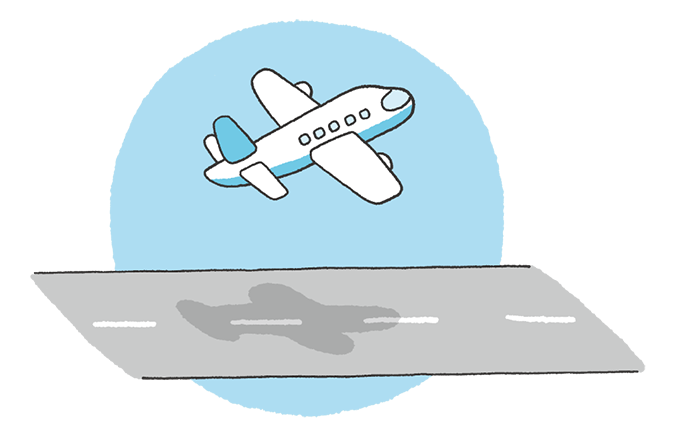
2021年末から翌年1月にかけて、アメリカで「5Gスマートフォンの電波の影響で飛行機が運航できなくなる」という騒ぎが起りました。アメリカの空港周辺の話ではありますが、日本からアメリカに向かう便も影響を受け、日本のニュースなどでも話題になりました。結局、アメリカの携帯電話会社が5G電波利用開始を遅らせ、そのあいだに航空機メーカが対策することになり、大きな混乱は回避されました。
騒ぎの原因は、飛行機が離着陸の際、地面との距離を測るための電波高度計で使用している電波と、5Gで使われる電波の一部が近い周波数を利用していたことです。5Gの電波が飛行機の電波高度計に干渉し、高度が正しく計測できなくなるという懸念が指摘されました。日本でも同じような懸念はありましたが、2018年に検討が行なわれ、飛行機に影響しないかたちで基地局が設置されることになったため、アメリカのような騒ぎにはなっていません。
そもそも飛行機の電波高度計に使われているのと近い周波数を5Gで使わず、ほかに使われていない周波数を使えば良かったという指摘もあるでしょう。しかし今の社会では、さまざまな用途で電波が利用されており、未使用の周波数はそうそうありません。実は、今回問題になった電波高度計に限らず、スマートフォン・携帯電話に新たに割り当てられた周波数は、それまで別の用途に使われていた周波数であることがほとんどです。
日本でスマートフォン向けに割り当てられてきた電波を見ると、4G用ではTV放送、テレビ局の中継回線、ワイヤレスマイク、タクシーなどの無線、なかには自衛隊が利用していた周波数もあります。これらの周波数は、もともとの利用を終了してもらう前提で、その「跡地」をスマートフォン用に割り当てました。
こうした電波の用途の変更は、有識者による議論をもとに総務省が「周波数再編アクションプラン」として策定しています。終了対象となった用途では免許の更新(再免許)が行なえなくなり、免許の期限が切れると、その時点で利用終了となります。
ただ、免許の有効期間は一般に5年間であり、有効期限切れを待つだけではなかなか用途の転換が進まないこともあります。そのため、近年のスマートフォン向けの周波数再編では「跡地」を利用する携帯電話会社が費用を負担して「終了促進措置」がとられています。例えば、終了対象になったワイヤレスマイクでは、新しい周波数用の設備への買い換え費用を携帯電話会社が負担するなどしています。
ここで挙げた4G用に割り当てられた周波数では、従来の用途での利用を完全に終了する方式がとられています。それに対し、5G用に割り当てられた周波数では、従来の用途での利用を完全に終了させるのではなく、互いに影響のない範囲で共用する方式がとられました。これらの周波数は、冒頭に紹介した飛行機の電波高度計や人工衛星との通信で利用されています。そのため、空港や衛星通信設備の近くに5Gの基地局を設置しないという対策がとられています。
さらに今後、スマートフォン向けに割り当てが予定されている周波数では「ダイナミック周波数共用」と呼ばれる方式が検討されています。例えば、屋外でのテレビ収録に利用する中継用無線は、収録時以外は使っていません。そこで、対象の周波数がいつ使われているかを管理するシステムを用意し、その時間帯以外はスマートフォン用に利用しようという方式です。これにより、既存の利用者の無線設備を入れ替えないまま、スマートフォンでの利用も可能にすることが考えられています。
周波数再編はスマートフォンに限った話ではなく、全ての無線利用に適用されます。ですが、スマートフォンを含めた携帯電話網の用途拡大、通信需要の増大を背景に、再編における“台風の目”的な位置づけになっているように思われます。
2025年の視点
携帯電話事業者への周波数の割り当ては、当該事業者の経営全般にも影響するため、大きな話題になります。ただ、記事でも紹介した通り、他の用途から転用された周波数帯を使い始めるには、かなりの時間を要します。例えば、2024年に割り当てが発表された周波数帯は、順調に準備が進んだ場合でも、利用開始が2030年になるというスケジュールが公表されています。報道などで話題になる時期と、実際に私たちがスマホで利用できるようになる時期に大きな違いがあるということも、トリビアの1つかと思います。
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです