ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
ぷろろーぐ 熱帯
IIJ.news Vol.190 October 2025
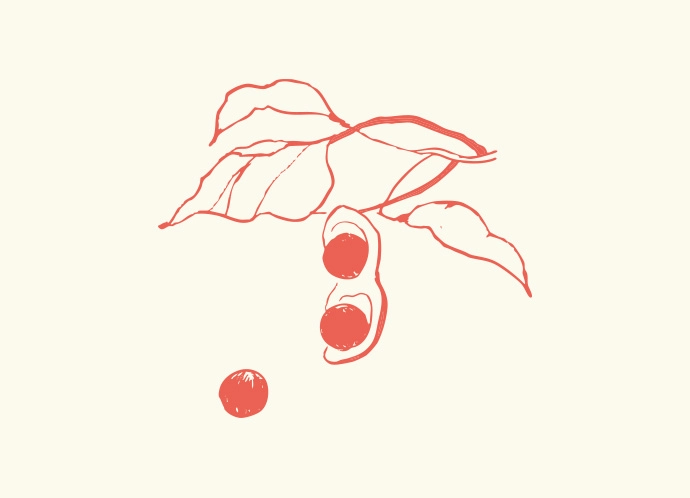
株式会社インターネットイニシアティブ
代表取締役 会長執行役員 鈴木幸一
「日本の暑さ、大変ですね。シンガポールは、28度から32度。安定していますよ」。
早々とシンガポールに移住してしまった友人から、そんなメールが届いた。1995年から数年ほど、アジアにインターネットのバックボーンをつくろうと、アジア各国の通信会社に出資をお願いして「AIH (アジア・インターネット・ホールディング)」という企業を設立した。中心となって推進したのは、IIJ、香港テレコム、シンガポールの政府系企業だった。8カ国の通信会社が出資に応じた。米国、欧州、アジアという3つの地域が、それぞれ共通のバックボーンを持って、インターネットの将来を担おうという発想だった。将来は、アジア各国にメッシュ型のネットワークを構築するという構想だったのだが、発足当初は、日本にトラフィックを集めて、米国や欧州とやり取りするかたちになってしまった。シンガポール政府の方から「鈴木さんは大東亜共栄圏をつくろうとする意図はないでしょうね」と揶揄され、韓国からは「東京ハブ構想はダメですよ」と、くぎを刺されたりしながらも、なんとか立ち上がったのだが、結局、各国との協調体制をつくることができなかった。
そんなことで、アジアを駆けずり回っていた頃、シンガポール、タイなど、各国の空港に降りて、タクシー乗り場に向かうと、ぼぉっとするような蒸し暑い外気に触れ、汗が噴き出した。その感覚こそ、東南アジアだったのだが、今やシンガポールに住む友人から、東京の夏の暑さと違って、シンガポールの暑さは常軌を逸したものではなくて、快適だ──そんなメールが届くようになった。
変われば変わるものだという感想よりも、地球環境が想定をはるかに超える速さで、変化を続けていることに恐さを感じてしまう。今や巨大産業となったITの基盤は、言うまでもなく、電力が支えているのだが、その電力をどのように供給していくのかについて、日本は明快な指針を出さないまま、時間ばかりが経過している。環境破壊などによる酷暑に対して、根本的な施策を講じる方向へむかうのか、あるいは40度近い酷暑に慣れてしまい、空調で室温を保つだけの対処に終わってしまうのか。肝心なことに立ち向かう施策は常に痛みを伴うのだが。
個人的なことを言えば、もともと私の身体は、感受性が鈍いのか、暑さ寒さに対して敏感に反応しなかったようだ。真冬でも火の気のない部屋で、何時間でも本を読み、掛け布団を掛けずに眠ってしまっても、風邪をひくこともなかった。夏は夏で「暑い、暑い」と、大人が音を上げていても、扇風機もつけずに長い時間、昼寝をしたり、ぽたぽたと汗をたらしながら机に向かって本を読んでいたらしい。
ただし、高齢者になった最近は、街頭から聞こえる「高齢者は熱中症が危険ですから、必ず冷房をつけてください」という親切な役所の忠告に従って、冷房を入れるようにしている。40度近い気温が頻発するのは、まったく新しい現象であり、昔の流儀では危険極まりないほど、怖い夏になってしまったのである。
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです